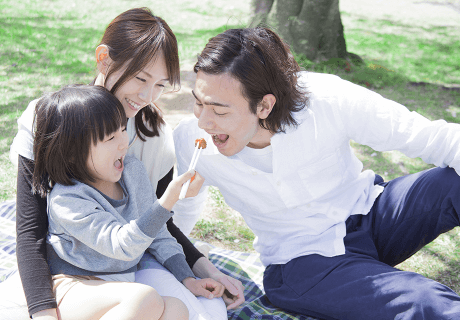ご挨拶Greeting
QOL(生活の質)の改善を目指した
整形外科として。

本教室は、1976年(昭和51年)10月1日における大分医科大学の開設から5年後の1981年(昭和56年)4月1日に、大分医科大学整形外科学講座として開設されました。その後、2002年(平成14年)4月1日付けで大分医科大学腫瘍病態制御講座(整形外科学)、大分大学との統合に伴い2003年(平成15年)10月1日に大分大学医学部腫瘍病態制御講座(整形外科学)となり、更にその後の再編に於いて2004年(平成16年)4月1日に現在の大分大学医学部脳・神経機能統御講座(整形外科学)が発足しました。初代教授は真角昭吾先生(昭和56年4月)、第二代教授鳥巣岳彦先生(平成9年12月)、第三代教授津村 弘先生(平成17年4月)、そして令和5年4月からは私が教授職を受け継ぎました。
整形外科は運動機能の維持・向上を重要視し、運動器疾患の予防・診療や治療を行う医療分野です。脊椎・脊髄疾患、関節疾患、骨・軟部腫瘍、多発骨折や骨盤骨折などの重症外傷、関節リウマチ、骨粗鬆症、スポーツや小児整形など、その治療分野は多岐に渡り、患者さんの痛みや不安に寄り添いながら、常に最新の医学知識と技術を駆使して治療にあたることが求められます。
運動器は人生を豊かに過ごすために欠かせない身体の構成要素です。人の一生において、小児期は成長と発達の重要な時期であり、運動器機能の発育も含めた全体的なサポートが必要です。子どもたちが健康に成育するため、運動器に対する専門的な医療を展開することが望まれます。また、労働の中核的な担い手として経済に活力を生み出し、社会保障を支える生産期年齢においても、スポーツや交通事故、転落などによって生じる外傷や運動器の疾病による時間的、機能的損失を最小限にするために先端的な知見を取り入れ、安全かつ効果的な治療を行い、健康的なライフスタイルを享受できるように努めるのが、我々の使命です。
日本は世界も認める長寿国です。しかし、我が国の平均寿命と健康寿命には依然として大きな差が見られます。我が国における平均寿命と健康寿命の差は、高齢化社会の進展に伴い、様々な運動器機能の課題や健康リスクの存在を浮き彫りにしています。「健康寿命の延伸」は整形外科にとって重要なテーマであり、運動療法を中心に予防医学の早期介入の有用性の啓発を通じて、QOL(生活の質)の改善を目指した診療を行っています。自立して元気に暮らすことができる、つまりQOLを重要視する考えは、国連で採択されたSDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)の目標の1つでもある「すべての人に健康と福祉を」にも繋がります。
大学病院の整形外科は、医療の最前線であると同時に、研究や教育の場でもあります。医療現場での実践的な知識や手技の習得などを行うことはもちろん、整形外科は手術が多く行われる診療科であり、新たな手術技術の開発や改良に伴い、常に自己を研鑽することが求められます。また、知識や技術だけでなく、意欲的なリサーチマインドを有し、コミュニケーション能力や人間性を大切にし、優れた医療従事者となるためのサポートを提供すると同時に、国際的な医学的情報や知識を学ぶことでグローバルな視野を持ち、多様な医療現場で活躍できる人材の育成も重要な使命の1つです。
この教室は、数十年にわたり医療の最前線で活躍し、多くの優れた医師や研究者を育ててきた歴史ある場所です。過去の教室の成果と伝統は、私たちが担うべき使命の重要な礎です。先人の残した足跡に学び感謝しながら、新たな展望に向かって挑んでいくのが私たちの責務だと考えています。これからも、大分大学福祉健康科学部や医学部先進医療科学科などの分野とも力を合わせて医学・医療の発展に貢献し、地域社会との結びつきを深めながら患者さんに寄り添う医療を目指します。今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
- 大分大学 医学部 整形外科学教室 教授
- 加来 信広
当科の沿革History
- 教室名
- 大分医科大学整形外科学講座
- 教室開設年月日
- 1981年(昭和56年)4月1日
大分医科大学は、昭和46年に文部省が発表した全国的な医師不足と無医大県解消のための医師増員計画に基づいて、昭和51年10月1日に開設した。
2002年(平成14年)4月1日付けで大分医科大学腫瘍病態制御講座(整形外科学)となる。
その後、大分大学との統合に伴い2003年(平成15年)10月1日付けで大分大学医学部腫瘍病態制御講座(整形外科学)となり、さらに、その後の再編に於いて2004年(平成16年)4月1日付けで大分大学医学部脳・神経機能統御講座(整形外科学)となる。
2008年4月1日より人工関節学講座を開設した。
当科の特徴Feature
生き生きとした生活を送るために、
私たちが出来ること。
人が生き生きとした生活を送るためには、姿勢を保つことに加え、立つ、歩く、物を持つなど自分の体を自由に動かすことが必要です。整形外科では骨・関節・筋肉・腱・靭帯・神経など、体を動かす機能に関わる運動器の疾患や外傷を診療し治療しています。手や脚の痛み、しびれ、関節痛、腰痛やケガなど日常生活や仕事、スポーツなどの趣味に支障をきたす運動器の障害が対象です。具体的には脊椎・脊髄疾患、脊柱変形、関節疾患、骨・軟部腫瘍、手の障害、骨折・脱臼、関節リウマチ、先天異常、骨粗鬆症などを治療しています。
疾病や外傷で運動器の機能を著しく障害された場合には、手術を行うことによりその機能を回復させることが必要となります。骨・関節のbiomechanicsの研究を応用したより低侵襲手術でよく曲がる人工関節置換術、脊椎・脊髄疾患に対する顕微鏡応用した脊椎手術なども行っています。
また整形外科では、手術治療のみでなく関節リウマチや骨粗鬆症に対する最新の薬物治療も行っています。さらに明らかにされていない疾患の病態解明や新しい治療法の開発にも取り組んでいます。